U2W #6 Report
- LAGS2 Reporter
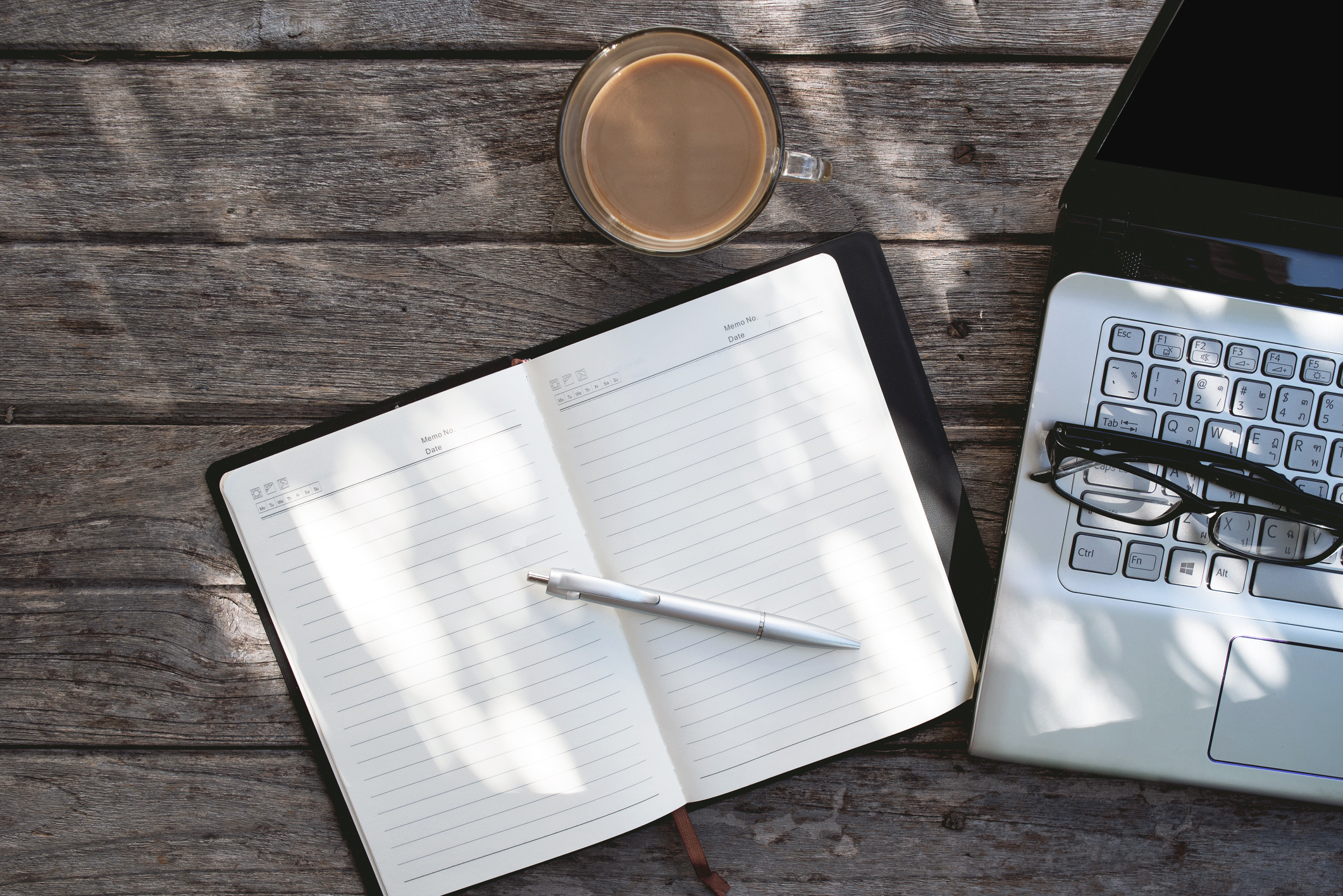
- 2020年7月31日
- 読了時間: 18分
更新日:2020年8月8日
第六回のスピーカーはイギリス、シェフィールド大学に留学中の吉本文香さんです。 イギリスのガーデン文化や大学でのデザイン教育について詳しく伺いました。

今日の内容
吉本さんについて
ランドスケープへの興味と留学までの道のり
シェフィールド大学のランドスケープ
植栽デザインとガーデン文化
日常生活
コロナの中で考えたこと
吉本さんからのメッセージ
質疑応答
吉本さんこんな人

95年 広島生まれ
幼少期、イギリス、ブライトンで過ごす
北海道大学農学部卒業
シェフィールド大学留学中
ポジティブ
ひょうきん
新しいもの好き、なんでもやってみたい
多趣味
強運の持ち主
ランドスケープへの興味と留学までの道のり
なんでランドスケープ
子どもの頃の伏線が大きく影響している。
自然と触れ合い楽しむものがたりの影響。
・ピーターラビット
・まほうのえのぐ
・ガンバの冒険シリーズ
・風の谷のナウシカ
→人間でないものと話したいという気持ちが育まれた
生き物係、早起きして通学路で鳥を探す。ウサギ小屋で過ごす昼休憩。
草月流いけばなとの出会い。
8歳からいけばなを習う。「いけばな=花との対話」という考え方を学ぶ。
思い通りにならない植物を扱う芸術を楽しみ、植物の多様性や美しさ、植物を使った空間芸術に触れた経験がある。

小中高で環境問題について勉強したことも大きな影響を与えている。 いきものに対して申し訳ない気持ちを持った。
公園とか、街にもっと緑があった方が良いのではないか、ということを考え、大学の進路を決め、北海道大学の花卉・緑地計画研究室に入った。
北海道大学での学び
サイクリングと農業風景を楽しんだ日々だった。
人間活動によって生まれた美しい風景、里山、道中で出会う人々の生活に触れ、地元、広島と全然違う植物が生えていること、動物との距離感が近いことに気がついた。
→人間活動が環境にもたらす良いこともあることということが気づきとしてあった。
花卉・緑地計画研究室では、美しい風景は管理されているということに気がついた。
・お金がかかる
・時間がかかる
・人手もいる
→改めて、自然と人の営みへの繋がりを感じ、ランドスケープアーキテクチャという分野への興味が強まった。

なぜ留学
元々、英語が得意で、そして留学に行きたいと思っていた。親からは語学留学ではなく「専門を持って留学しなさい」と言われており、ランドスケープという専門分野を学びに留学しようと思った。(普通じゃないことをしたい欲も留学をする一因になっった。) シェフィールド大学を選んだ理由は、 幼少期を過ごしたイギリスに行きたいと思っており、「イギリス ランドスケープ」で検索で検索したところシェフィールド大学が出てきた。そして、イギリス全体的にガーデンの文化が強く、Landscape Gardeningを押し出す大学が多いが、シェフィールド大学はLandscape Architectureを強く押し出しており、より広い空間設計について学べるのではないかと思い選択した。 (イギリスのど真ん中に位置するため、旅行に行きやすいのではという気持ちもあった。)
シェフィールド大学のランドスケープ
シェフィールドの街
古い教会と新しい建物がごちゃ混ぜになっている街。 イギリス第五の都市だが、”The Biggest Village”と呼ばれていて、人の温かさが残る街。ステンレススチールが発明され、かつて、スチール産業で栄えた。 世界最初のフットボールチームが生まれ、ヘディングが生まれた。現在は2つのサッカーチームがある。 ピークディストリクト国立公園が街中から車で20分ほどの距離にある。 ヨーロッパ一緑の多い街と言われており、“The Greenest City”と呼ばれており、国立公園も近くにあり、街中にも緑が多い。 ピークディストリクト国立公園はシェフィールドプレイグラウンドとも呼ばれていて、市民が週末に歩きにきたり、と人の生活のすぐ近くに緑がある。

シェフィールド大学はシティキャンパスで、シェフィールドの街中にいくつかの建物を持っていてそこに通う。学生自治がイギリスで一番良いと言われている。


シェフィールド大学のカリキュラム
MA Landscape Architectureコース 1年目 デザインのスキル デジタルスキル ・様々なデザインの流れ ・様々なスケール(公園〜都市計画) 2年目 関心に合わせて授業を選択 卒制・卒論 Landscape Studiesというコースは1年で卒業することも可能。
デザインエクササイズ
屋外に出かけてスケッチをしたり、デザインエクササイズをすることが多かった。 エクササイズでの学び ・物の見方を変えてみる。 ・「偶然」に意味づけしてみる。 ・いろんなプレゼンの仕方を学ぶ。 ●トポグラフィーに関するエクササイズ 先生が印刷してきた2dのパターンを無理やり3dに変えて、色の濃淡やパターンの特徴から凸凹を見出す練習をした。 ●パターンに関するエクササイズ Design Languageという授業では、曲線や直線が混ざっていると一貫性のないデザインになるため、デザインの言語を自分なりに作り出す必要がある。 一貫性のあるパターンを考えるため、一枚の平面から立体を作る練習をした。 先生はSerendipityという言葉をよく話していた。素敵な偶然に出会ったり、予想外の物を発見すること。

●自然のパターンに関するエクササイズ ピークディストリクトにでかけて、自然の中にあるパターンやテクスチャを見出す。 朽ちた落ち葉とまだ新しい落ち葉や樹々のあり方から時間の流れというテーマを見出し、ゆっくり時間が動き堆積するという提案を行った。

卒業制作
エクササイズ等で学んだ、デザインの発送の仕方が一番役に立った。
Special Project is all about expressing “How you see the world differently.”
プロジェクトサイトは、地元広島 新しい埋立地に計画されている緑地。これまで大学では北海道に行ったり、シェフィールドに行ったりと地元について向き合うことが少なかったので、地元を対象地として選んだ。
実はあんまり海辺に行かなかった、海辺に工業地帯があり近寄りがたい、泳げる印象がないといった理由から広島の海に親しみを感じていなかった。
親しみを感じないことから、海で起きている環境問題へ目が向いていないのでは。
一方、潮の満ち引きを強く感じる厳島神社では海への親しみを感じることができる。
潮の満ち引きが海への親しみを導くデザインの起点になるのでは。
潮の満ち引きを可視化するデザインを目指す。
潮と月には深い関係があり、月には太陰暦など日本文化のつながりがある。 “Cultural Sense of Time in Japan”。西暦は時間を棒状に感じているが、和暦では時間をループするサイクルとして捉えられている。
日本の文様にも同じ輪という考えが表れている。
藍染にチャレンジし、そこで出てきたパターンを地形に当てはめてみるなどのチャレンジをした。潮の満ち引きによりパターンが徐々に変わるパターンが生まれる。
といった過程を経て、日本の文化を色濃く表しながら潮の満ち引きにより海への親しみを誘導するデザインを提案。

卒制の詳細はこちらから。 プロセスの9割は成果物にならなかったが、でも役立った。 無駄に思えてもとりあえずやってみる。
シェフィールドのガーデンスケープと課外活動
Gray to Green
シェフィールドは洪水がよく起きることから、Gray to Greenというプロジェクトが街中で行われている。雨をうけるような街路の植栽をすることによって洪水を防ぐデザイン。 手間をかけない→多年生の提案を行うことが多い。 一年を通して楽しめるための、花暦の作成を丁寧に行ったデザインに気をつけている。 できるだけ植物を違和感なく混ぜていくような工夫(Breakdown the edges)が行われている。できるだけ折り重なるように植物を植える。 街の至る所に植栽デザインがあり、面白く、勉強になる。

イギリスの住宅とガーデン
イギリスの家を上から見ると、フロントガーデンとバックガーデンがあり、バックガーデンは裏の家のバックガーデンと繋がっている。連続する緑が生態系の保全につながっている。動物がバックガーデンを渡って通れるよう、柵の下に小さなトンネルが作られていることも。街路樹が少ないが、フロントガーデンが道路の緑を足していて、歩いていて楽しい。
“Just sit in the garden”という言葉がよく使われる。
ガーデンはイギリス人に非常に親しみのある空間で、ちょっと座って談笑するなど日々を過ごす場所の一つになっている。
日本庭園とは違っていて、植物がごちゃ混ぜになっていて、しかし、生き生きとしているというのがイギリスのガーデンの特徴。
Flower Showへの参加
ガーデニングの祭典、花壇デザインコンペに挑戦をした。 五感がテーマのコンペだったので聴覚に注目して提案。音楽を表すような植栽計画を提案。 植物を買い集め、育てる経験からは、植物が思う通りにコントロールできないということや、描いたプランと実際の作る過程の違いを強く感じ、良い経験になった。結果的には銀賞を受賞することができた。 ショーが始まると、イギリス人からガーデンについて山のような質問を受け、彼らのガーデンへの熱量を感じた。


チームシェフィールド大学からはコース外の活動だが、大学から金銭面、知識面でサポートをしてもらい、非常に良かった。

日常生活と奨学金
留学=生活
留学=海外で生活すること 食べ物について、美味しいが、見た目への配慮が薄い、味付けや調理法に繊細さがない、などの違いがあると感じた。 Sandwich & Wrapが非常にコスパの良いご飯。さくっと食べられる食べ物。お店の人との会話や外で食べるということがとても楽しく良い経験。 ホームパーティーにもよく招かれ、楽しくご飯を食べている。
ロータリークラブ奨学金
お金だけでなく色んな体験が得られるおすすめの奨学金。 給付型、親善大使としてイギリスのクラブのイベント等に参加することが役割。 ホームステイができ、ホストファミリーと楽しい時間を過ごした。親善大使として大勢の前で地元広島についてプレゼンをすることもある。暖かい目で見てもらえ、度胸もつき良い経験になった。 たくさんの人に会えることがとても良かった。 友人として接してくれる。遊びに連れて行ってくれたりもする。
ロックダウンによる変化
シェフィールドの街の変化
2020年3月17日にイギリス全土でロックダウン。
日常が一変したが、みんなが街に励まし合うようなコメントを残しあう。Social Distanceを保ちカフェに並ぶなど細々と生活は続いた。
一方で、屋外公共空間の価値を感じている。
自転車の売り上げがすごいというニュースを聞いた。“Work from Home”の影響で、家族との時間が増え、家族でサイクリングやジョギングする人を見かけた。
コロナで苦しい状況だが、それはそれでハッピーな風景だと感じた。
また、路上に座る人々が増えたということも発見としてあった。
カフェ、レストランのテイクアウト営業をしていたので、道端のちょっとした段差に座ってご飯を食べる人が増えたため、そういう活動を積極的に促す都市空間の設計もありうる。
庭でBBQを食べていた人が、庭に人を呼べなくなったため、路上でBBQをする人も。面白い変化だと感じた。

文香さんの変化
2020年3月14日に学部棟も閉鎖。 卒制の締め切りが迫っていて、人に会えないのは辛くなるのではないか、と危機感が。 メンタル第一にと思い、ニュースを見るのをやめ、外に出かける、卒制もやるけど、とりあえず好きなことをやる、必死にtake it easyの精神で生きることにした。この状況下でできるいろいろなことにチャレンジ(スケボーなど)したところ、些細なアウトプットから卒制につながるアイデアが生まれることも。 コロナ前は 手の届く範囲の話、現実味のある範囲のことを考えていたが、 コロナが広まった後は 内へ内へ、あるいはもっと遠くのことを考える時期になった 例えば、身近の動植物に目を向けることが増えた。 その一方、ゲド戦記を見直し、世界全体のことについて考えたり、分野を問わずに勉強するようになった。社会、経済、資本主義、食や命についてなど。非科学的なもの、哲学、宗教、文化などについて目を向けるようになり、科学だけを盲信するのは違うのではないか、ということを感じた。 「What’s the health」、「トイビト」はおすすめのドキュメンタリーと勉強サイト。
吉本さんからのメッセージ
ランドスケープアーキテクトって。
人も自然も平等に愛し、面白がって、よく観察する人だと思う。
そして、色んな視点、尺度を持っている、学び続ける人が多い。
切り離されてしまいそうなものを“場のデザインを通じて繋ぎ”、うまく回るようにしたい人たちなのではないか。(ナウシカ的な人なのでは。)
そのためには、バックグラウンドはなんでも役立つ。
「ランドスケープを学ぶのにバックグラウンドを気にすることないよ。」

今後やりたいこと
修論は「シェフィールドの市民農園について」を書く予定。そして、9月からオーガニック栽培の農家でインターンし、2021年1月末に帰国する予定。 「食・農業とランドスケープそしてそれを伝える教育が自分のやりたい道ではないだろうか。」
質疑応答
Q. イギリスで日本人として学ぶという姿勢に強さを感じた。広島生まれで、イギリスで学ばれているということで、卒業制作で時間の顕在化にチャレンジしたことが日本らしさがよく表れていたのでは、と感心した。食べること、人間としての生活についてどういう活動をしようとお考えですか?(Kさん)
A. 農学部では作物を育てるという経験もしており、一方、デザインも楽しかった。 周りに優秀な人がたくさんいてデザインをすることは自分の役割なのか悩むこともあったが。。 プラクティカルなことは社会人から学ぶことはできるので、学生のうちは飛んだ発想を形に落とし込むことが大事だと思うので、設計の道で頑張ってもらいたいと感じた。(Kさん) 植物が思い通りにならないということを感じたので、自分で土を触って育てるということを経験したいと考えている。その気持ちからインターン先の活動にも繋がった。 そういった経験が説得力につながると思うので頑張ってください。(Kさん) Q. ガーデンに熱を向けている人がなぜ食にこだわりがないのか。(Kさん) A.
大航海時代に外の世界に行けたのは食べ物にこだわりなかったからとも聞いた。 ガーデンも様々な植物を混ぜるところなど、几帳面さはないのかな、と感じた。 Q. こだわっている人もきっといるだろうし、層が厚そうだと感じた。街中にで食べ物を作るような場はあるのか? A. 市民農園をGISを使って分析していて、そういう場はたくさんあるように感じている。そこへのアクセスがあるのか、ということを調べようと思っている。 会社の理念で食べ物を選ぶということが一般的な考え方。 C. 中国・四国地方で活動されると良いのではないだろうか。(Fさん) C. 農に関心があるということに嬉しく感じた。サステイナブルな社会を作るという上で非常に大事な視点だと思うので、今後も頑張ってほしい。Incredible Edibleというプロジェクトもチェックしてほしい。(Mさん) Q. 最近、パトリック・ブランという植物学者兼アーティストの方の作品を拝見する機会がございましたが、設計者も一般の人も、もう少し人間以外の動植物と向き合う姿勢を持たなければいけないのではないかな、と最近しみじみ感じます。私もランドスケープとか、農学とか、植物学とか、真面目に学んでみたくなりました!とても貴重なお話を誠にありがとうございます。予定がありまして、お先に失礼致しますが、また機会がございましたらお話、是非、伺いたいです!どうもありがとうございました!!!(Fさん) A. 新山口に彼の作品があり、とてもおすすめです。Q. 影をスケッチするのいいね。留学生はどこの国が多いですか?日本からの留学生は減ってると聞きましたが。(Tさん)A. 中国人が多い。半分以上が中国語で中国語が飛び交うことも。一年上に日本人の人もいて、交流があった。 千葉大学の学生もシェフィールドに来たり、ということも。 U2Wに関われている人を頼って、良い仕事をしていくのが良いのではないか。出会った人との縁を大事すると良い仕事を幸せな気持ちで取り組めると思いますよ。(Tさん) Q. デザインの発想の仕方についてお話があったが、どういう風に発想を広げるべきか詳しく聞かせてください。(Mさん) A. ストーリーテリングのために、どういうステップを踏むかということがデザインではないか、と思う。 身近なものに目を向ける気がつくことがゴロゴロある。クラスメートと話すことで新しい意見をもらうことができた。井戸端会議やU2Wもそのような場として使うと良いのでは。 C. バックボーンがたくさんある人にランドスケープに関わってほしい。 日本は戦後から復興や復旧を長いことやっているように感じている。見えないところの基盤がしっかりとしているように感じている。基盤整備とその上のデザインをするという文脈だと思う。 A0層のデザインをしている。そこでランドスケープが活躍できるのではないか、と感じている。(Mさん) C. 技術職の資格を7つ持っていて、その際は認定ランドスケープアーキテクトという資格がなく、そういう資格を作ろうと思って資格を取っていた。宮崎では認定ランドスケープアーキテクトの資格を持っている人が1人しかいなくて、それらを広めるために活動をしようと思っている。学生時代は広く学んでもらいたい。働き始めてからは深堀してもらえると良いのでは。(Mさん) Q. 私もロータリー奨学生ですが、将来はロータリアン(ロータリークラブに参加する人)になる予定ですか?世界的な活動をされている人が多いので、そういう方向性に参加する予定は? A. 最初は経済的な理由で参加したが、いい人ばかりで感動した。 ロータリアンになるための条件をクリアできれば参加したい。違う業種に参加するという意味でも参加したいと思う。自分が助けてもらった分、ロータリーという形で支援したいと思う。 どのような形でも社会貢献したいと思う。 Q. 卒業制作(広島と海)に至った理由についてと自転車についてもう少し聞かせてください!発想の仕方が非常に伝わるプレゼンだった。そもそもの出発点が聞けたら嬉しい(Mさん) A. ずっと外ばかり見てきた気がしたので、これを機会に地元について関わるのも良いかな、と思い選んだ。被曝建物の再開発についても考えようと思ったが、チューターに「メモリアルがたくさんあるが、さらに作る必要はあるのか?」という疑問を投げかけられ、違うサイトを探し、海との関わりについて考え始めた。 最近、自転車に再度乗るようになってきて、サクリングロードが延びていたことに気がついた。 自転車レーンがあるのだが、そのレーンに路上駐車している車が多く、あまりサイクリングに向いていないかもしれない。 ロンドンではサイクリングロードの計画があり、これからの計画に期待したい。 Q. シェフィールド市の都市の密度やスケールは人々の「歩く」や「チャリ移動」にどれぐらい適性があると実感としてお持ちでしょうか!? 特にヨーロッパ諸国はコロナ禍のロックダウンを逆手に取って色んなWalkable Cityや歩きで完結する都市スケールを実現するための社会実験をやってると色んな記事で目にします。そのあたりのトレンドも含めてシェフィールドやイギリスの社会の都市についての認知の変化の現状について教えてください!(Iさん) A. リングロードという市街を一周する車道があり、その中は密に都市開発されており、その中はあまり車で移動するのに適していない。ロンドンもその大きいバージョンというイメージ。そのため都市の中での生活はとても歩きやすい。 しかし、リングロードがシティセンターと郊外住宅を分断しているという側面もあり、それらをどう繋ぐか、ということが大学の課題としても出るほど大事なテーマだと考えられている。 シティセンターが盆地になっていて、住宅街にいくまでには坂を上ると言った地形になっていて、自転車向けの街ではないかもしれない。 Q. コロナがどう都市を変容するのか、ということを考えていて、イギリスで様々な提案が出ていてると聞くが、都市でそのような実験が起きているという肌感覚はあるか?(Iさん) A. シティ中心部で、歩道が拡張されている、花壇で道を閉鎖し、歩行空間を確保するなどの変化を感じた。店の壁を塗り替えると言った変化を感じた。ポジティブな変化があった。 Q. 卒業制作非常に素晴らしかったです!日本文化をランドスケープデザインに反映されているアイデアが非常に興味深かったです。イギリスと日本の自然感の相違点 や、イギリスの文化が景観に反映されていると感じられる場面がありましたら、教えていただきたいです。(Fさん) A. 日本とイギリスの自然観の相違点は、宗教の違いがベースにある。キリスト教では終わりがあるという考え方だが、日本では、八百万の神や輪廻と言った考え方がよく表れていて イギリス式風景庭園の考え方をもとにしたガーデンが多い。人工的に広大な風景(丘、川、見るための建物)を作るという庭がある。人工的にそのような風景を作るということが人間と自然を切り離して考えているということを感じた。 Q. イギリスの日本庭園を見に行ったところ、海外のジャパニーズガーデンだなと違和感があったが、逆もしかりなのだろうか?(Fさん) A. イギリスで学んだ人が日本でイングリッシュガーデンを作っている。(上野ファームなど) 日本のイングリッシュガーデンはいい線いっているのでは。 Q. 「ナウシカ」ってどこまで世界で通じるんだろう。。?イギリスでは通じましたか?(Mさん) A. ジブリ好きの友達が多く、話に上がることが多い。 トトロとか猫の恩返しを知っている人が多いが、ナウシカは少し知っている人が少ないかも。 C. ロードオブザリングなど、言語から土地まで全てを作った作品。文学とランドスケープの繋がりは非常にあるように感じる。風景と文学はピクチャレスクのように深いつながりがある。(Yさん)Q. 動画で紹介もされてましたが、bioswaleやrain gardenはシェフィールド全体でよく見られますか?(Kさん) A. 一度シティの方で大きな洪水災害があり、Gray to Greenというプロジェクトが始まった。川沿いなどに災害も含めた考えたプロジェクトが増えてきた。工事中のものが非常に多い。 Q. イギリスは、アメリカやオーストラリアの留学先の大学とどういう部分が違うと思いますか?(Kさん) A. 厳しい気候の中、土地柄と合わさってプランティングデザインをしっかりと考えられているように思う。 C. 自分のことを強運だといっている人は自分で動ける人なので進路について心配していません。(Eさん)
ライター中島より
イギリスというとガーデン文化が有名ですが、大学でのスタジオの活動でも、詳細な植栽計画を提案されたり、街中にもたくさんのガーデンがあったりなど、ガーデン文化につながる考え方を知るのにとても良い環境で学ばれているな、と感じました。
また、デザインエクササイズで学ばれた発想を広げ方が卒制にもよく表れていて、素晴らしかったです。人の生活と自然を繋げる仕事、ランドスケープアーキテクチャをする上で、土や石、植物を触る経験を大事にされたいという考え、とても共感いたしました。今後の活躍に期待しております!
中島悠輔





コメント