東京・メルボルン・ベルリンのランドスケープを渡って
- LAGS2 Reporter
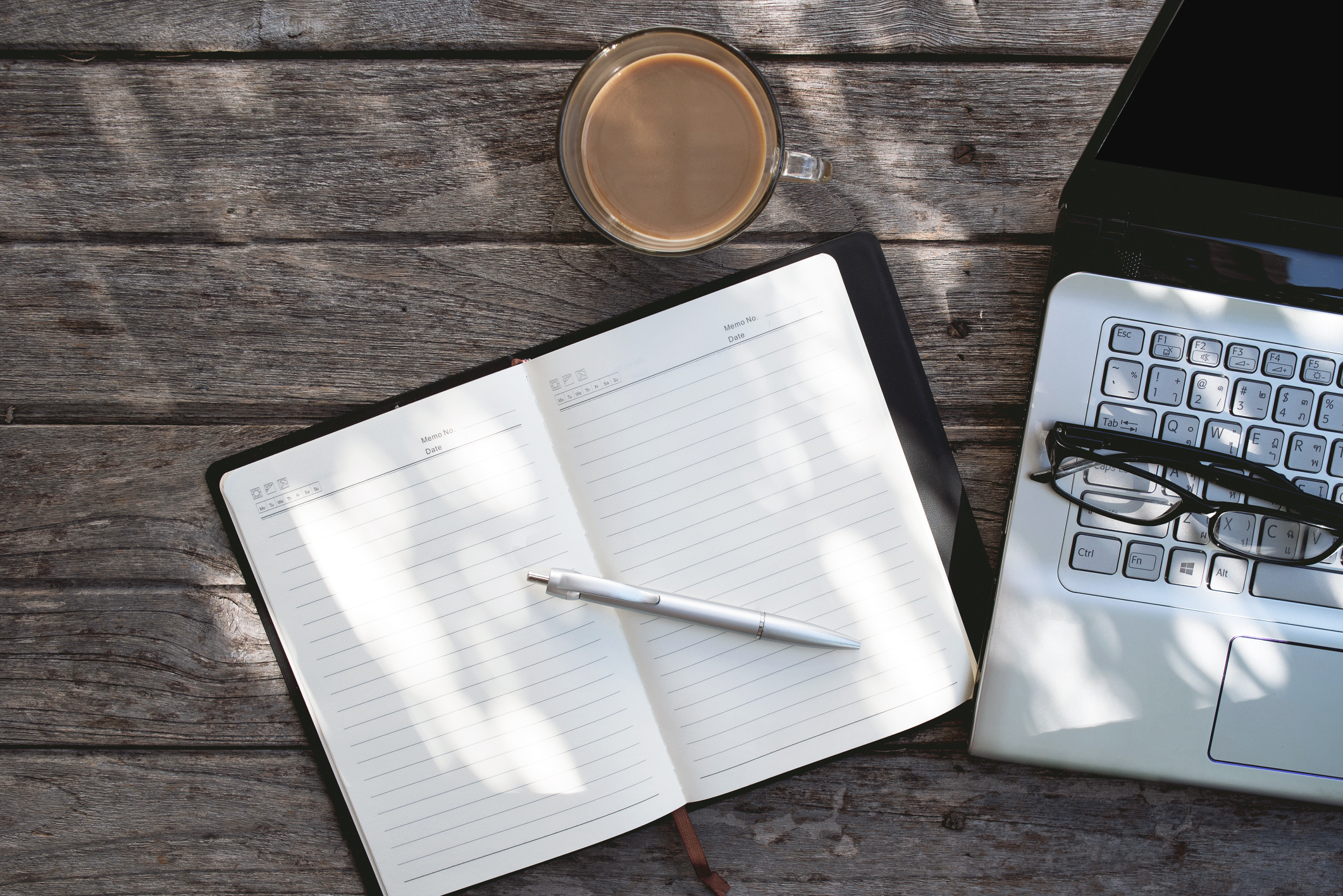
- 2021年9月27日
- 読了時間: 6分
更新日:2021年11月10日

自己紹介
初めまして。愛知県出身、ドイツ、ベルリン在住の中島悠輔です。
東京、メルボルン、ベルリンに住み感じたそれぞれの街・ランドスケープについてお伝えできたらと思います。(ベルリンはまだ来て1ヶ月ですが笑)まずは少しだけ自己紹介させて頂きます。

僕は1歳から6歳をオーストラリア、シドニーで過ごしました。その後、名古屋の郊外のエリアに戻りました。シドニーでは毎日ビーチに行き、釣りをしたり、芝生で遊んだりしていましたが、愛知に戻り用水路はヘドロが詰まり魚はおらず、たまに行く名古屋の街並みも高層ビルが建て並び、自然がなく、息苦しさを感じていました。この頃から自然や空間に興味を持つようになりました。
その後、東京大学農学部で生態学を学び、東京大学大学院にて特に緑地計画を中心に都市計画を学び、ランドスケープアーキテクチャという言葉に出会いました。本格的にランドスケープについて勉強したいと思い、東大の大学院の修士課程を修了後、メルボルン大学に留学し、2020年にランドスープアーキテクチャの修士課程(Master of Landscape Architecture)を修了しました。2021年8月までメルボルンのランドスケープ事務所Acer Landscapesにて設計・施工・管理に携わり、2021年9月からドイツ、ベルリンに来ました。
この記事では東京、メルボルン、ベルリンのランドスケープの違いについて紹介出来たらと思います。
目次
‐ 東京のランドスケープ
‐ メルボルンのランドスケープ
‐ ベルリンのランドスケープ
‐ 街の違いから感じるランドスケープの方向性の違い
東京のランドスケープ
私は2011年から2017年までの7年間東京で過ごしました。
大学生として色々な場所で遊んだり、カメラを持って公園や庭、建築を見に行ったり。
東京を歩いていて感じるのは建築の力が強いことです。
丁寧に作られた美しい建築が多い。海外の奇抜なデザインの建築は少ないですが、シンプルな落ち着いた細部がしっかりとしている建築が多いように感じていて、私はとても好きです。一方で何をするにも建築の中に入らないとできない息苦しさがあるような気もしています。勉強は学校、仕事は会社の事務所、食事はレストラン。建築が窮屈に建て詰まっていて、川辺に座ってぼーっと本を読んだり、ピクニックしたりするような人はほぼ見かけません。(そもそも川辺は柵で覆われている。)
これまで撮り溜めた東京の写真を見返すと建物と建物の隙間の小さな自然や広場空間の写真が多い。こういう小さな屋外空間が東京のランドスケープの特徴かな、と。少しずつこういう空間が増えたら嬉しいです。
また、東京のランドスケープは歴史や文化の上に成り立っている所がとても好きです。歩いていて、2000年以上の歴史、特に江戸から明治、大正、昭和、平成の歴史を感じることができます。地形や地名、道路・建築・広場の形にヒントがあり、それに気が付いた時、東京って面白いなと楽しくなっていました。
撮りためた東京の写真は『東京の中』という電子書籍にまとめています。
もし良ければこちらもご覧ください。
メルボルンのランドスケープ
メルボルンは2018年から2021年までの3年半を過ごしました。
この頃は真面目に色々な公園やランドスケープ作品を見て回っていました。
メルボルンの街はゴシック様式の古い建物とモダンな高層ビルが混在しています。地震がなく、建築上の制約が少ないことからエッジが曲線だったり、上に向かってねじれていたり、と奇抜なデザインの建築を見ることが出来ます。ピカピカとしたビルが多いのは日差しが強く光を反射するガラスをデザインに多用するためだと思われます。 この伝統とモダンデザインの混在はランドスケープアーキテクチャについても言えます。100年ほどの歴史のあるイギリスの風景式の公園が残っている一方、近年開発が進んでいるドックランド等のエリアではモダンなデザインの公園が増えてきました。
建築・ランドスケープ分野でのモダンなデザインは1950年代以降のオーストラリアのモダニズムの流れを受けているのだと思いますが、色や形状が派手で曲線や直線の主張がきついような印象があります。
メルボルンのランドスケープはオーストラリア固有の動植物とアボリジニの歴史・文化があることだと思います。メルボルンの真ん中を流れるヤラ川は市民の日常的な散歩コースで、ユーカリやアカシアの森を楽しむことが出来ます。モーニントン半島の海岸沿いには塩耐性・風耐性のある背の低い植物が。ペンギンを見ることも出来ます。キングレイクというエリアはイネ科の植物が広がる金色の山が連なっています。雄大な自然とそこを分け入る冒険心がオーストラリアのランドスケープの最も強い特徴ではないかと思います。
また、これらの自然と共に何千年も生きてきたアボリジニの文化もしっかりと残っています。アボリジニの文化を理解し伝える場というのは現在のオーストラリアのランドスケープアーキテクチャの大きなテーマとなっています。
ベルリンのランドスケープ
2021年9月にベルリンに移ってきて約3週間が経ちました。街・ランドスケープが今まで見てきたものとまた違い楽しんでいます。
様々な歴史・文化を感じさせる街並みが残りつつもバウハウス建築の流れを受けた非常にシンプルなモダン建築が混ざりあう街という印象です。厳しい建物の高さ制限など厳しい都市計画を感じますが、街中には川や運河沿いの公園、広場、などたくさんの人が溜まる場所がたくさんあります。地べたに座って話し込んでいる人もおり、強い自由を感じさせる都市です。
来てすぐに感じたことは、雑草がかなり多く、剪定をあまりしない、非常に自然的なランドスケープが多いということでした。そもそも自然主義な人が多いようです。庭でハーブを栽培するなど実用的に使っている人が多く、見た目を美しく整えあまりエッジのはっきりとして英国風のガーデンは好まれていないのかもしれません。 また、ベルリンの人はナチスやベルリンの壁などの社会的な統制への反発という気持ちが非常に強いらしく公園・広場のデザインや使われ方にもこの意識が表れているのかもしれません。
街とランドスケープの違い
写真から少しでも伝わったらと思うのですが国・街が違うとランドスケープが大きく異なります。どれが良いかという事ではないと思います。それぞれの街には違う文化・歴史があり、ランドスケープも違ってきます。これから目指すべきランドスケープのあり方も違ってくるでしょう。
僕は東京のランドスケープがとても好きです。奇抜さはあまりないですが、日本らしい落ち着いたデザインはもっと評価されて良いと思います。2021年、メルボルン大学の教授Jillian Wallis氏が『The Big Asian Book of Landscape Architecture』という書籍を出版しました。これまで西欧中心のランドスケープが注目されることが多かったですが、おそらくアジアの近代的ランドスケープを本格的に紹介・評価しているの書籍ではないかと思います。海外のランドスケープと日本のランドスケープを両方見比べ、冷静に評価しながら今後、日本がどのようなランドスケープを造っていくべきなのかを考えていけたらと思います。























































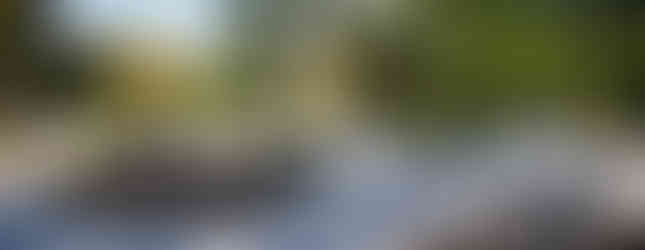





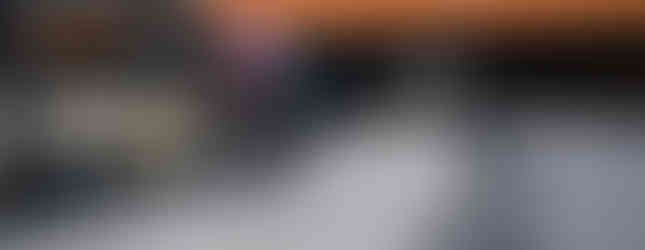











































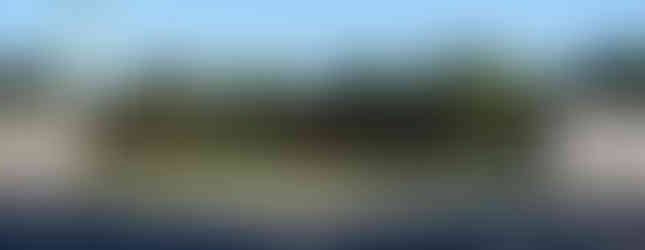




























コメント